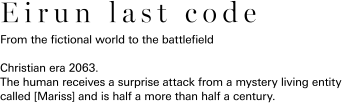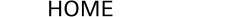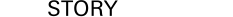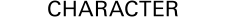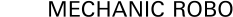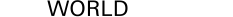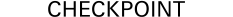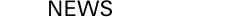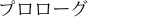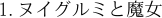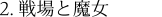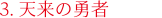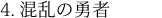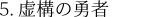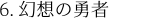幕間
【ドール・ワルツ・レクイエムⅡ 第十一話 〔そしてまた一人〕
2070年3月29日 放映】
———————— 回るアニメーション映像 ————————
宇宙空間に、閃光が走った。
巨大ロボットの兵団が並ぶ。横並びにビームを放った。
【真紅の戦闘機】が、猛スピードで敵の弾幕を避け続ける。
真っ赤な装甲板。アルファベットの〔A〕のような形状のボディ。
底面部のミサイル発射管から、立て続けにミサイルが射出される。先頭部のスライドした装甲板の間からは機関砲が伸び、銃弾を噴き続けている。
敵の一団が吹き飛んだ。ロボットの兵隊たちが次々と壊されていく。
一対一〇〇とも二〇〇ともいえるこの戦場で、主導権は真紅の戦闘機にあった。
しかし、それでも少年は焦る。
自機の突破力を頼りにした決死の特攻……軍人としての素養が滲みついた少年自身も賢い選択とは思えなかった。しかし、この特攻の是非によって友人たちの命運が決まる。
少年が目指しているのは球体状の巨大建造物だった。
それは敵が秘密裏に開発した、戦略レベルの大量殺戮兵器だ。
ブースター付近にミサイルが着弾する。コックピットを衝撃が襲った。
少年は頭を強くぶつける。血の珠が浮かび、モニターに当たった。少年はそこで初めて怪我を負っていたことに気付く。
しかし少年は怯まない。
熱くなった体と、冷え込んだ意識がそれでも自機を前へ押し上げる。
前へ。前へ。そうして少年はたどり着く。
小惑星かと錯覚するほど大きさ……少年にはそれが悪意の塊に見えた。
「ジン!」
少年はトリガーを引く。
機体中腹にある砲身の発射口に、青い光が溜まる。
「後は任せたぞ!」
放射される大光線——最高の威力をもったムーンブラスターが一対の矢になる。
次の瞬間、白い光が広がった。
真紅の戦闘機も機械の兵団も、球体と一緒に光の中へ消えていった。
Ⅲ 天来の勇者
白色の意識が覚醒に向かう。世界が急速に色を帯び始めた。
「こ、れは?」
少年は自分がどうなったのか、何一つ分からない。意識が覚醒すると、混乱は助長した。
周りを見渡すとさっきまで少年がいた場所と、今いるこの場所は全くの別世界だった。遅れて更に気付く。機体の自由が、全く利かなくなっている事に。
「海!? それに重力だと!?」
少年は声を上げる。操縦桿の右横に在るボタン群を高速でたたき出した。
「アンノウン接近! 距離一五〇〇! 一四八〇!」
「この忙しいときに! どこの国の馬鹿だよ!」
役員が言った。雷鳥の視線が立体マップのある右側モニターに向けられる。〔?〕の黄色マーカーがどんどん急降下していくのが分かった。
「衛星映像! 出ます!」
女子役員が報告する。中央モニターの映像が切り替わった。
画面に映ったのは、【真紅の巨大戦闘機】だ。
アルファベットの〔A〕のような形状のボディ。後部には大きなブースター。紅の装甲板が全体を覆う。機体底面に二門の砲頭を構える。
謎の戦闘機は、第弐富士との距離を、急速に縮めながら降下していた。
「生途会の兵器データベースに該当ありません。ネイバーを含め、現在まででロールアウトされた物の中にも……全長三〇,五メートル、規格外の大きさです。米軍の新型?」
その報告に何人かが眉をひそめる。
職質上、生途会の役員は戦術兵器に詳しい者が多い。
通常、戦闘機は運用の観点から二〇メートルを越える物は少ない。
が、この戦闘機は三〇メートル以上ある。そのサイズともなると長距離航行を想定した、施設破壊用の爆撃機かと疑ったのだ。
「どうして……あんな物が、」
紫貴が愕然とした声を漏らす。役員たちが浮足立つ中、雷鳥が当該戦闘機へのコンタクトを命じる。一人の女子役員が慌てて有線電話の受話器を取った。
コックピット内にコール音が鳴る。
「通信? こんなときに!」
機体設定の再構築に大忙しだった少年は声を上げた。
『そこの戦闘機のパイロット! 止まりなさい! ここは対マリス戦・特別指定区域です! それ以上の接近は領空侵犯とみなし——』
「すまない! ちょっと待ってくれ!」
せわしなくキーボタンを叩きながら、少年は応える。通信先でくぐもった声が聞こえた。少年は構わずにインプットを続ける。
『国家の安全保障に関わるんですよ! 今のあなたの行為は!』
「だから少し黙っててくれ!」
声を荒げ、少年は歯噛みする。動かす指を止めず、今の自分の切実さを通信先の女性に告げた。
「今、墜落中なんだ……」
少年とコンタクトをとった女子役員が受話器を持ったまま動かなくなる。
「セレン! すぐにそこから離れて! 飛行機が落ちてくる!」
まず紫貴が動いた。セレンに通信を送る。
しかしデストブルムの回線からは少女の泣き叫ぶ悲鳴しか聞こえてこない。一拍遅れて他の役員たちも、止まっていた手を動かし始める。
「生途会より本部管理中隊(CCV)! アンノウン戦闘機が墜落中! アンノウン戦闘機が墜落中! 場所はポイントD7! デストブルムとクイーンがいる海岸! 至急、関係各所に通達されたし! 繰り返す!」
慌てる生徒達の傍ら、雷鳥は怪訝そうな顔で中央モニターの戦闘機を見ていた。
そして、衛星映像に映るクイーンもまた、その動きを止めていた。デストブルムを取り押さえたまま四つの目を天へと向けていた。
コックピット内で、メインモニターの外枠(フレーム)ランプが赤から緑に変わる。
「よし!」
メインモニターに迫る岩肌——少年は操縦桿を両手で握り、それを一気に引き上げた。
「上がれぇええっ!!!!」
戦闘機のブースターが点火……機体が地面すれすれの所で持ち上がる。
真紅の戦闘機が縦に旋回した。爆発的な加速で上昇を果たす。
少年の口から大きな安堵が漏れる。操縦桿を握る手が緩まった。
「お騒がせしました。もう大丈夫です」
そう言って少年は、状況の整理に意識を持ち直す。
モニターの上半分は蒼海が広がっていた。下半分は見たこともない島だ。
あちこちから煙が昇る。聞こえてくる砲声から、少年はここが戦場だと理解する。島の地形と自分の記憶を照らし合わせてみる。だが記憶をかすりもしない。
少年は胸中で舌打ちをした。
まさかよりにもよって落ちてきたのが見知らぬ惑星で、しかも戦闘中だなんて……巻き込まれるのだけは避けなくては、と少年は通信先の女性に釘を打つ事を試みる。
「まず第一に、本機に戦闘介入の意思はありません。本機はある作戦行動中で宇宙にいたのですが、その……気付いたらここに落ちてきてしまったのです」
『こちらは氷室義塾・生途会会長の九重です』
コックピットに先ほどの声とは別の、凛とした声が届く。
『たいへん良い御趣味をされているようで。しかし、もしこれが、こちらの緊急要請に対する米軍側の回答というのなら、私達にも考えがあります。UNを通して此度の件、断固、追求せていただきます』
「べいぐん? ゆーえぬ?」
少年は首を傾げる。何やら皮肉めいた彼女の言い回しもそうだが、少年の知る限り、そんな機関名など聞いたことがなかった。
『最後通達です。以降、確かな回答を得られなければ撃墜します』
少年は焦る。こちらとて彼女の発言は冗談に聞こえるのだが、声色から彼女が本気だと
察した。少年は取り成すように返す。
「じょ、冗談ではなく、ここは地球のようですが、場所は? 経緯度の高さからしてワノモトかコリナースのどこかでしょうか?」
『……いいかげんにしなさい』
彼女の声に怒気が混じる。
少年が更に焦ったその時、コックピットの右下のランプが赤く光った。
—攻撃シグナル!?
少年は目を丸くする。機体・右側の全スラスターを最大噴射——機体を乱暴にシフトさせる。直後、コンマ数秒前まで自機のあった空間に、黒い球体が現れた。
驚いて海岸部をモニターで拡大する。顔が二つある化物が、こちらに向けて一本の手をかざしていた。何かは分らないが、少しでも反応が遅れていたら直撃だった。
「クイーンの無差別物質消去(IME)を避けた!?」
戦闘機の回避映像を見て、雷鳥が勢いよく立ちあがった。
『まて! こちらに戦闘の意思はない! 繰り返す! こちらに戦闘の意思はない! 攻撃をやめろ!』
少年の声が司令室に流れてくる。今度は生途会の役員たちが首を傾げる番だった。
「誰に言ってるの? まさか……マリスに?」
「マリスに言葉なんて通じるわけないじゃない」
「もうっ!」
調子を狂わされっぱなしの紫貴はインカムのスイッチを再び入れた。
「ベルファルカスの新型か!? あんなシュプリームドール、見たことが無いぞ!」
少年は機体を旋回させながら映像データを解析しだす。だが、あの生々しい巨体に照合するデータは無かった。
『マリスと意思疎通なんてできる訳ないでしょう! 撃墜されるわ! 早く逃げなさい!』
「マリス!? あの怪物のような奴のことか!?」
また飛んできた知らない言葉に、少年の頭はいよいよ処理が追いつかなくなる。混乱していると、今度は老婆の声が流れてきた。
『混乱してるとこ悪いんだがね、私は氷室雷鳥。一応、本作戦の最高司令官ってことになってる』
司令官という単語が、軍人である少年に大きな緊張を走らせた。
『急にで悪いんだが、一つ頼まれてくれないかい? 海岸に黒いのが見えるだろ? そいつを、ちょろっと助けてはもらえないかね?』
『司令!?』
司令官と名乗る者に言われるまま少年は海岸を見る。一方が劣勢なのは分かった。でも何を言っているのか、(軍に所属する人間の視点から考えると)少年には理解できなかった。
「おっしゃる意味がよく分かりませんが?」
正体不明、どんな危険を孕んでいるか分からない異分子に協力を要請するなど、少年の隊の軍規に照らせば大問題である。
少年は司令官と名乗る者の狙いを探し始める。でもそれは、すぐ出来なくなった。
『まぁ、そういわずにこれを聞いてくれよ』
『やぁああああぁ! もうやぁ! 出してぇ!』
届けられたのは、泣き叫ぶ女の子の声だった。
「なんだ……これは」
少年は顔を青くする。声からして、叫んでいるのは年端もいかぬ少女と推察できた。
『その黒いのに乗ってるパイロットなんだけどね。まぁ、ほぼ民間人みたいなもんで、今の状況に耐えられるような訓練を受けてないのよ。こっちの言うこと、聞いてる余裕もないみたいなんだわ』
「そんな……声を聞く限り、まだ子供じゃないか!」
『で、だ。簡略して言うと私らは今、化物と戦っている。エイリアンでも巨大怪獣でもなんでもいい、とにかくそんなようなもんと殺し合いをしている』
「待ってくれ……化物?」
少年はすぐに異形の解析を始める。
熱反応を確認すると有機生体反応、生物である事が分かった。調べた結果が、老婆の発言に信憑性を持たせる。少年は真っ向から内容を否定できなくなった。
『いいから最後まで聞きな……その顔が二個ある奴がいるだろ。その気持ち悪いのを殺さない限り、この戦闘は終わらない。あいにく戦力不足でね。その黒いのがやられたら、いよいよマズイ。そこから島が見えるだろ。その島の連中、残らず皆殺しにされる』
言われて少年はすぐ見つける——鉄の城壁に囲われた都市群を。古城にも、要塞のようにも見える島である。この怪物は、あの島を目指しているとでもいうのか。
事態は少年の想像を絶していた。葛藤が胸をたたき始める。
『あんたの乗ってるの、見たところ戦闘用だろ? 少し隙を作ってくれるだけでいいんだ。あとはこっちで全部やる。そっちから見れば、私らは顔も見た事の無い他人だが、それでもここには数万って数の人間がいる。簡単に見殺しに出来る数には思えないんだ。あんたはどう思う? 謎の戦闘機パイロットさん』
「もし、それが本当なら……しかし、」
少年は悩む。
もし、この司令官と名乗る者の言うことが本当だとしたら。
今も泣き叫んでいるこの少女の命が消えそうになっているというのなら……居合わせてしまった以上、見殺しになんてできない。しかし、
「申し訳ありません、その要望には応えられません……私は軍人なんです」
立場と責任。決定を下すとき、必ずその二つは効果を発揮する。少年は、感情の赴くまま闘っていい権利など持ち合わせていなかった。
『だからなんだい? 人を助けるのに小難しい理由が必要だとは思えないけどねぇ』
「仮にも司令官と名乗る者が……なんだ、その言い草は!」
少年は老婆の声をかき消す。また、揺れ続ける自分を諌めるように声を張り上げた。
「俺は軍人だ! どんな理由があろうと、他国の戦闘に許可もなく介入するなんてできるわけないだろう!」
通信先から複数人の驚く声が聞こえた。
気づけば大声を上げてしまい、熱くなった分だけ気は沈む。
老婆の返答は、しばしの沈黙の後だった。
『そうか、じゃあ好きにしとくれ。あいにくこっちはアンタを捕まえてどうこうなんて余裕、今はないからね。こっちの領海から出ちまえば一先ずは安心だよ。ついてたね、坊や』
軽い口調で通信はきられる。しかし、コックピットには依然、あの少女の泣き声が流れてきた。少年は歯噛みをする。そのやり方を汚いと思った。
「誰か、」
デストブルムの全方位モニター——セレンの前には、クイーンの顔面が広がっていた。
『その黒い機体のパイロット、聞こえるか』
何か聞こえた気がする。しかし、モニターに映るクイーンの顔が。その口の端を持ち上げて、口内からこちらを見る無数のポーンが、セレンには怖くて堪らなかった。
「たす……けて」
セレンはもう一度、誰も応えてくれないコックピットで呟く。すると——
『いいから聞け! バカヤロウ!』
背筋が跳ねるほど大きな声で怒鳴られた。
『いや……命令、もう、ヤ』
少女の声が返ってくる。それを聞いて少年は絶句した。
——……可哀想に。
少女の声は凍えきっていた。精神の均衡に危うさを感じさせるほどに。いったい、どんな目に遭わされれば、こんな悲愴な声が出せるのか。 ぶつけ先の分らない怒りが少年に芽生える。怒りは、この少女を助けたいという気持ちを大きくした。
「命令なんてしないよ。すまない、大きな声をあげて」
少年は優しく言う。この少女に、今、自分ができる最善をしようと思った。
「辛かったら喋らなくていい。その怪物が怖かったら目を閉じて……俺の話を聞いてくれるだけでいいんだ。あとはしなくていい。難しくないだろ?」
少年が言い終えると沈黙が流れた。つまり彼女は自分の話をちゃんと聞いてくれている。
「君は素直なんだな。偉いぞ」
少年は優しい声音を意識する。また、敵の攻撃にも全神経を集中させた。
「じゃあ次は、自分の好きな物を思い浮かべてみよう。それだけで頭をいっぱいして……どうだ、少し楽にならないか? あと、ゆっくりでいい。思い浮かべたら、それを口に出してみるんだ」
再び沈黙が流れた。敵の動向が少年の心を急かす。少年は神経をすり減らしながら少女が声を出してくれるのをじっと待った。
『……シロ』
通信が入る。声には確かな生気を感じた。少年の顔がほころぶ。
『シロ、好き』
「そうか。それはペットか何かかな? お腹を空かせてたら、っ!」
突然の攻撃シグナル——少年の相貌が大きく開かれる。
操縦桿を真横に。戦闘機のブースターが吼えた。きりもみ回転して機体がシフトする。ギリギリのところで戦闘機は謎の黒い球体を回避した。
「……大変だ」
少年は小さく安堵する。どんな攻撃か分からない以上、当たるわけにはいかない。また、話している少女も不安がらせてはならない。
——見知らぬところにやってきたと思ったら、また大ピンチだ。
自嘲気味な笑いが零れる。だが、こんな状況でも少年の肝は座っていた。数々の死線を潜り続けての今日がある。少年にとっては許容内だった。
「君はこんな場所にいちゃいけない……家に帰ろう」
少女に優しく投げかける。通信先で少女が驚いた声が聞こえた。彼女はしばらく押し黙る。今度の沈黙は長かった。やがて少女の方から少年に通信を送ってきた。
『あなたはわたしを……助けて、くれるの?』
涙に濡れた小さな声で少女が聞く。少年はそれに頷いた。
『ああ。俺の全部で君を助ける。だからもう泣くな』
そう言うと、少年の紅い瞳に強い光が宿る。
司令室の誰もが、少年とセレンの会話に耳を傾けていた。
立体マップの[?]マーカーは、クイーンの周囲を行ったり来たりしている。
『幸い、今、君を捕まえてるそいつの注意はこっちに向いている。動きを見る限り、君よりも俺にご執心のようだ。今のうちにどうにかして、そいつから離れる事はできないか?』
『みさいる、もう無い。すぐれものもダメ……もうまごのて、一本しか………………あ』
『何か、あるみたいだね』
撹乱機動をとりながらも、少年はセレンの言葉を聞き洩らさない。
「セレンが……持ち直してきている」
「パニック症状の扱いに慣れているみたいだね。経験か、それとも持ち前の何かなのか……クイーンを前に、なんてタマだい」
紫貴は少年の手際に驚いている。雷鳥も感想を加えながら、自席の光学モニターのパネルキーを叩く。あの戦闘機がクイーンの攻撃を避けてからというもの、雷鳥の関心は今やあの少年に向いていた。
セレンの心に光が指す。恐怖に縛られて動けなかった身体は、次第に自由を取り戻していった。
「ク、ロ」
セレンの恐怖を投影して沈黙を守っていたデストブルム——新たな命により、滅灯させていたアイカメラを光らせた。
四本のマシンアームのうち、三本は敵に掴まれている。垂れ下がっていた最後の一本が鞭のように大きくしなった。
クイーンの腕が二本、弧を描いて飛ぶ。腕の付け根から噴水のように血が噴き出した。
魔女はこの好機を逃さない。
取り戻した蔓も加勢させる。血飛沫を飛ばして別の腕も切り落とした。
デストブルムのマシンアームは、小口径IMEカノンの発射位置を調整するための発射台としてだけでなく、白兵戦用の武器としても機能する。
デストブルムの蔓の前では、厚さ数メートルの装甲板も発泡スチロールと変わらない。
「きゃ!」
血ダルマになったクイーンにセレンが嫌悪感を抱く。
デストブルムの大きな帽子から青い炎が吹き出した。推進力が生まれる。離脱ついでにクイーンの顔もスラスターの炎で焼き焦がした。
「上出来だ!」
真紅の戦闘機が転進する。一対の砲門をクイーンに向けた。
「数度に渡る警告は受け入れられなかったと判断する! 本機は防衛行動を取らせてもらう!」
苦しいが、順序を踏んだ事実は残す。危険回避が困難な場合、少年には自衛権の行使が許されていた。
『待って! 充分です! あとはセレンにまかせて! クイーンに通常兵器なんて!』
制止の声が入る……が、既にトリガーを引いた後だった。
青色の粒子が一対の砲口にチャージされる。蛍の群れが砲口に吸い込まれるようだ。
青い光は大きくなり、爆ぜた。光が砲弾となって射出される。
『『『!!』』』
通信先からざわめく声。
マリスの顔があった腹部と胸部には、少年の狙い通り、大穴が二つ開いていた。
「まだだ!」
戦闘機の砲身が真ん中で割れるようにスライドする。中からドラム状のシリンダーが露出した。虹色の光を発して回転を始める。
再び光が放たれた。光のマシンガンだ。
滑空しながら、真紅の戦闘機はクイーンの身体をズタズタに穴だらけにする。
ゆっくりと伸ばされた手が……、前へ進もうとした身体が……、光の銃弾で抉れてゆく。
戦闘機が通り過ぎるとクイーンは既にその動きを止めていた。
「敵兵力の無力化に成功……こちらの損害、無し」
少年はため息をついてシートに身体を預ける。戦闘機の背後ではスローモーション再生をかけるように、穴だらけになったクイーンが浜辺へ崩れ落ちた。
「なんだい……今のは」
雷鳥は咥えていたタバコを落とす。
「か、解析不能。形状から類推するにプラズマの一種か何かとしか、」
男子生徒が慄然と報告する。紫貴は息を呑んで首を横に振っていた。
「クイーンを、倒したというの?」
作戦時間・二時間二三分。戦闘は、謎の戦闘機の介入により異例な形で終結を迎えた。
デストブルムのコックピット内——真紅の戦闘機の映像が、何度も別再生された。
セレンは目に涙を溜める。これは感激の涙だった。
「あなたは……誰?」
セレンは真紅の戦闘機にそう問うた。
時が一八時を刻む。
辺りは茜色に染まる。夕暮れの一時を感じさせた。
ここは氷室義塾施設グラウンドで、平時は校庭として使われる場所だ。生徒達が見物できる場所を求めてひしめく。その数は一〇〇や二〇〇では済まない。
戦闘終了後、島を離れようとした謎の戦闘機は、遅れてやってきた戦艦九隻に囲まれた。示威的な武装解除命令を海上自衛隊が行うと、現場は一触即発の空気になる。
そこへ雷鳥が介入して場を収めた。それから真紅の戦闘機をここへ誘導する。
もっとも……生途会がオープン回線のまま、戦闘機のパイロットを誘導してしまったので騒ぎがここまで大きくなってしまったのだが。
中には、腕に包帯を巻いた葵や、治療を受けた機兵部の面々もいた。
野次馬の参列に一人が加わる。
——良かった。まだ来てないみたい、
紫貴だった。どこかそわそわした様子である。
一方で、リムジンを筆頭に、何台ものハイヤーが数珠つなぎに校庭に止まった。数人の護衛を引き連れ、最後は雷鳥が校庭に降り立つ。
「総帥自らが出向かなくても……安全とも言い切れません」
「巻き込んだのは私だからね。労いの言葉一つ言わないってのも後味が悪い」
進言するSPを無視し、雷鳥は校庭の中央へ向かう。
雷鳥たちの真向かい、数十メートル先——誘導棒を振る生徒たちの指示に従い、ゆっくりと巨大戦闘機が降りてくる。
突風が校庭の砂を巻き上げる。雷鳥は目を閉じること無くその様を見続けた。
風が治まり、真紅の戦闘機が衆目にその姿を晒す。
「……デカイ」
「うわー、真っ赤っかですねー」
葵は呟く。後輩の女子部員も感嘆声を上げた。鋭角なボディと紅の装甲板は、嫌でも目を引く。軍事兵器としては少々、派手すぎるように葵は思った。
戦闘機の底面部が開く。
ウインチのモーター音を鳴らしてロープが自動的に降りてきた。ロープの先にあるステップ状の金具に片足を掛け、一人のパイロットがその姿を現す。
パイロットは誘導してくれた生徒に簡単に敬礼すると、雷鳥の前に立った。
「……ふぁ」
紫貴はパイロットに目を奪われる。紅潮する頬を冷ますように両手を添えた。
「こりゃあ、随分な男前が乗り込んでたもんだ」
肩をすくめて雷鳥は笑う。
少年は、戦闘機と同じ、真紅のパイロットスーツを着ていた。
赤がタイトに身体を包む。鈍い光を放つ、肩や胸部分のプロテクターが印象的だ。月の形のエンブレムが左手の甲に付いている。
身長は一七〇後半といったところか。シャギーの入った黒い髪。顔つきはやや女寄りだが目鼻筋ははっきりとしている。女受けしそうな甘いマスクだ。
瞳は黒く、日系の十代後半か、二十代前半くらいの少年だった。
「イメージと、ピッタリ」
紫貴は、とろけるような声を漏らす。
少年は警戒しているのか、周りを横目で見回している。
「助けてくれてありがとう。謎の戦闘機パイロットさん……そして初めまして。この島のオーナー、氷室雷鳥だ。さっきまで坊やを振り回してたババアだよ」
雷鳥は意図的に破顔して見せる。そのシワくちゃの笑顔を見て安心したのか、少年の持ち上がっていた肩が少し下がった。
「お礼状の一枚でも書かなきゃいけないね。この保管領の最高責任者としてお願いするよ。名前と所属、良かったら教えてもらえないかい?」
雷鳥にそう言われ、少年は逡巡する。数秒ほど思考を巡らす。それから意を決したように顔を上げた。少年は直立しなおして雷鳥に敬礼する。
「月勢圏クローバー王国、ラインハルト軍——」
淀みない一連の動作が少年の兵役を物語る。
指揮官向きの、とてもよく通る声だった。全ての生徒が耳を疑う。
彼の言う、国と勢力……それを聞いた事の有る者と無い者で、校庭が二極化された。
「オーション第七銀河大隊、特別偵察艦ベガスター所属——」
軍事に携わる者の間では有名である自分。
正体を明かすことを躊躇う少年の心中など、全くの杞憂だった。代わりに、ここでは別の意味で有名なその肩書きに反応できたのは、集まる生徒の二割くらいだ。
全ての者が、聞きなれない単語に唖然となる。
「エイルン=バザット大尉であります!」
少年は最大限の敬意を込めて挨拶する。
静まりかえった空間で、少量の乾いた笑いが起こる。
その後、数箇所から同じような笑いが聞こえたのを少年の耳は拾っていた。